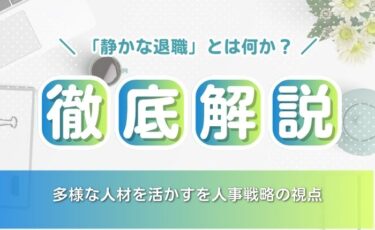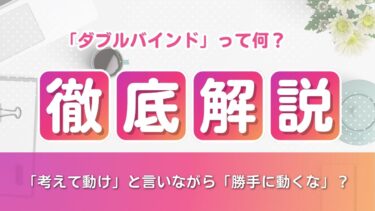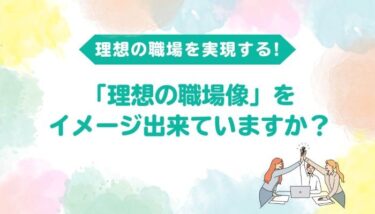毎年のように続く最低賃金の引き上げ。
ここ数年は、全国平均で50円前後ずつ上昇しており、数年前と比べると1時間あたりの賃金差は数百円にもなります。
この傾向は、パート・アルバイトを多く雇用する小規模企業にとって大きな影響をもたらしています。中でも「評価していないのに昇給せざるを得ない」という状況に、経営者の戸惑いや悩みが表面化しています。
本来、企業には人事評価制度があり、社員やパートスタッフの働きぶりや成果に応じて昇給や賞与が決定される仕組みがあります。ところが近年は、法定の最低賃金に合わせて評価とは無関係に賃金を引き上げざるを得ないという現実に直面しているのです。
最低賃金の引き上げがもたらす「評価なき昇給」
例えば、最低賃金が1時間あたり50円上がれば、1日6時間・月20日勤務のパートさんの人件費は月6,000円、年間で72,000円の増加になります。複数名のパートを雇用していれば、その影響はさらに大きくなります。
そして、ここで問題になるのが「昇給の根拠」です。これまでの人事制度の考え方では、昇給は評価に基づいて決定するものであり、業務の成果や成長に対して報いるものです。しかし現実には、成果や成長に関係なく、自動的に賃金が上がる状況が続いています。
その結果、評価制度の形骸化や、社員やパートからの「評価の意味がないのでは?」という声が出始めることも。制度が制度として機能しなくなるリスクもはらんでいます。
パートだけでなく、正社員にも影響が
最低賃金アップの影響は、何もパート・アルバイトに限った話ではありません。実は、正社員の処遇にも波及しています。
例えば、最低賃金の上昇にあわせてパートの時給を上げた場合、「時給換算すると、正社員とパートの差がほとんどない」という状況が起こることもあります。これは、正社員の立場から見るとモチベーションの低下につながりかねません。
また、「パートの賃金が上がったから、正社員の基本給も見直さなければ…」というプレッシャーも生まれ、結果として全体の人件費が膨らんでいきます。
このように、最低賃金の上昇は、企業全体の賃金バランスを崩す可能性を持っているのです。
人件費だけが増える…その前に業務の見直しを
では、どうすればよいのでしょうか?評価がないままに昇給だけが続けば、経営を圧迫し、評価制度の意味も薄れてしまいます。
そもそも、時給が上がるということは、それに見合った「業務の質」や「難易度」も向上あるいは改善する必要があるということではないでしょうか?
これまでと同じ仕事をしていて、ただ賃金だけが上がる――それは経営的にも、組織的にも持続可能とはいえません。だからこそ、まずは現状の業務を見える化し、見直すことが必要なのです。
そこで重要になるのが、「業務の見直し」と「役割設計」です。特に小規模企業では、ひとりの従業員が担う業務の幅が広く、業務の棚卸しがされていないケースも多く見られます。
1.業務の棚卸しで現状を可視化
まずは、「誰が」「どのような業務を」「どのくらいの時間で」行っているかを把握することが第一歩です。業務を分類していくと、以下のように分けることができます。
- 定型的・反復的な業務(マニュアル化しやすい)
- 判断が必要な業務(担当者の知識・経験が必要)
- 新しい提案や改善活動など、創造性が求められる業務
このように整理すると、どの業務を誰に任せるべきか、パートと正社員でどのように役割分担すべきかが見えてきます。
2.業務のIT化・自動化で効率アップ
定型的な業務については、ITツールやクラウドサービスを活用することで、効率化が可能です。
- 勤怠管理 → タイムカードからクラウド打刻システムへ
- 経費精算 → Excel集計からアプリ入力と自動集計へ
- 請求・支払い → 紙管理から会計ソフト連携へ
こうした業務のIT化により、限られた人材でも十分に回る仕組みをつくることができ、業務に対する生産性=コストパフォーマンスを高めることができます。
3.人事評価と業務内容の連動を図る
業務を見直したうえで、評価制度も現実に即したものに見直す必要があります。単なる「出勤日数」「時間」だけでなく、役割の幅、改善提案の実施、後輩指導の有無なども評価基準に加えることで、パートや正社員の意欲を高めることができます。
「評価していないのに昇給」という違和感を、「この働きがあったからこそ上げられた」という納得感に変えることが大切です。
持続可能な賃金設計のために
最低賃金の上昇は、今後も続く可能性が高いと見られています。単にコストとして受け止めるのではなく、業務の質や仕組みを見直すきっかけとして前向きにとらえることが、これからの経営にとって重要です。
特に小規模企業では、「採用が難しい」「人が辞めやすい」といった課題も重なり、限られた人材に頼るしかない状況もあります。だからこそ、今いる人材の力を最大限に活かす業務設計と、納得感のある評価制度が、企業の持続的な成長の鍵となります。
まとめ:評価制度の再構築と業務見直しがカギ
- 最低賃金アップによって、パート・正社員ともに「評価なき昇給」が起きている
- 人事評価制度の意味が薄れ、賃金バランスが崩れるリスクがある
- まずは業務の棚卸し・役割の再設計・IT化で生産性を見直す
- 評価制度を現場と連動させることで、納得感ある昇給に
「評価なしでも昇給せざるを得ない」という矛盾を、制度と仕組みで乗り越えることが、経営の安定と人材の定着につながります。
人を大切にしながら、無理のない賃金設計と働きやすい環境づくりを一緒に進めていきましょう。