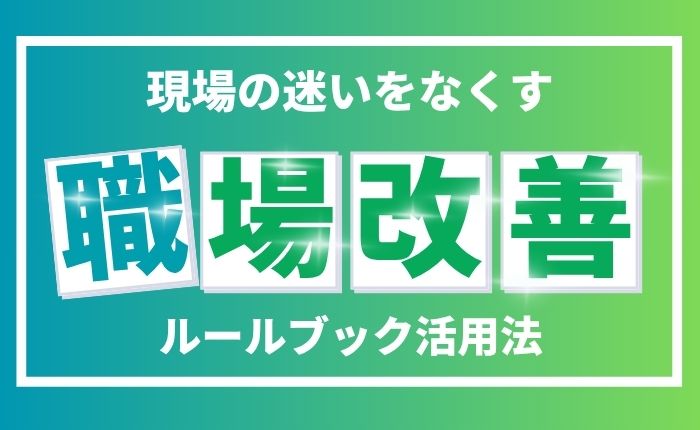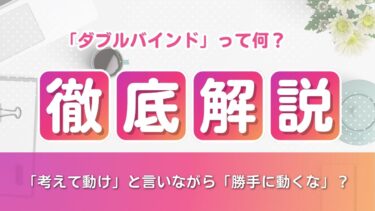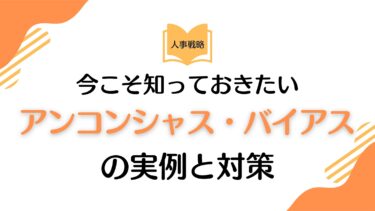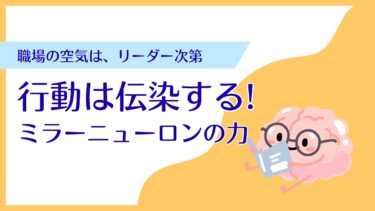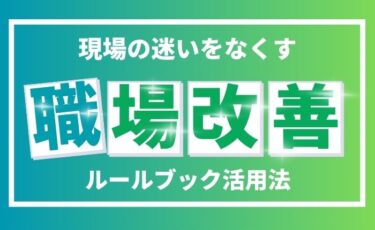はじめに|なぜ職場で判断がバラつくのか?
現場で「どう判断したらいいのか」と迷う場面は少なくありません。AさんとBさんで対応が違ったり、日によって判断基準が変わったり──。こうしたバラつきは、最終的に顧客対応の質の低下や、社内トラブル、社員の不安につながります。
実はこれ、「個々の能力ややる気」の問題ではなく、組織としての判断軸が明文化されていないことが原因です。では、なぜ判断軸が整わないのでしょうか?
就業規則だけでは足りない理由
多くの企業には就業規則があります。しかし、就業規則は法律上必要な最低限のルールであり、現場の日常的な判断や動きを具体的に示すものではありません。
たとえば、
- 社員同士のちょっとしたやりとり
- イレギュラー対応時の優先順位
- 新しい状況に対する判断
こうした現場のリアルな判断場面には、就業規則は対応していないことが多いのです。
その結果、社員一人ひとりが「これでいいのかな?」と迷い、上司の指示待ちになったり、独断で動いてトラブルになったりします。
現場で迷わないための判断軸とは
現場で迷わないために必要なのは、細かなルールを網羅することではありません。
「私たちの会社は、こんなとき、こんな考え方で判断する」
という判断軸を明文化することです。
判断軸があれば、
- どの社員でもブレずに動ける
- 新しい状況でも自分たちで判断できる
- ルールにないから動けない、という事態を減らせる
といった効果が生まれ、組織としての柔軟さと一貫性が両立します。
職場のルールブックとは?役割と特徴
この判断軸を形にしたものが、「職場のルールブック」です。
ルールブックは、法律的なものではなく、
- 組織の価値観や行動指針
- 現場での判断基準
- チームとしての約束事
など、「私たちの会社らしさ」を表すものです。もちろん、就業規則の内容をさらに現場に即したわかりやすい表現で記載するのもいいですね。
そのため、自社の課題や目指す方向性をもとに、オリジナルで作ることもできるのがルールブックのメリットでもあります。
ルールブック導入で変わる職場
実際にルールブックを作成し、運用していくことで、職場には次のような変化が生まれます。
- 社員から「どうしたらいいですか?」と聞かれることが減る
- チームで判断基準が共有され、仕事がスムーズに進む
- トラブル時にも「こうすればいい」がわかっている
- 経営者や管理職の負担が減る
つまり、「迷い」や「不安」が減り、やるべき仕事に集中できる環境が整うのです。
ルールブック作成と運用のポイント
では、実際にルールブックを作るとき、どんなことに気をつければいいのでしょうか。
- 経営者や管理職の考えを言語化すること
- 価値観や理想の職場像、行動指針などを、まず言葉にします。
- 現場の声も取り入れること
- 現場で起きている迷いや困りごとをヒアリングし、ルールブックに反映します。
- 「実際に使えるか」を意識すること
- 難しい言葉や曖昧な表現を避け、社員が読んで理解できる内容にします。
- 作ったら終わりにしないこと
- 周知・運用・定期的な見直しを通じて、職場に根づかせます。
まとめ|迷わない職場をつくる第一歩
ルールブック作成は、単なる「ルール整備」ではありません。
- 経営者の考えを伝えるツール
- 社員が迷わず動ける仕組み
- 組織の一体感を生む土台
として、組織づくりや人材育成にもつながる重要なステップです。
「なんとなく判断していた」「場当たり的に対応していた」状態から脱却し、
「私たちはこう考え、こう動く」という判断軸を全員で共有する。
それが、これからの組織運営に求められる姿ではないでしょうか。
まずは、「どんな判断軸が必要か」から、一緒に考えてみませんか?
▶ 『職場のルールブック作成』サービスの詳細/初回相談のお申込みはこちら
※ ご相談のみでもお気軽にどうぞ。
「うちも判断軸を整えたい」「まずはどんなルールブックが必要か相談したい」
そんな時は、ぜひお気軽にご相談ください。
現場の課題やお困りごとを伺い、自社に合った“使えるルールブック”をご提案します。
人事労務に関する、実務に役立つ情報や最新動向を
メールマガジンでお届けしています。
気軽に読める内容ですので、よろしければぜひご登録ください。
▶ メールマガジン登録はこちら
※ メルマガ登録ページ(当事務所ホームページ内)に移動します。