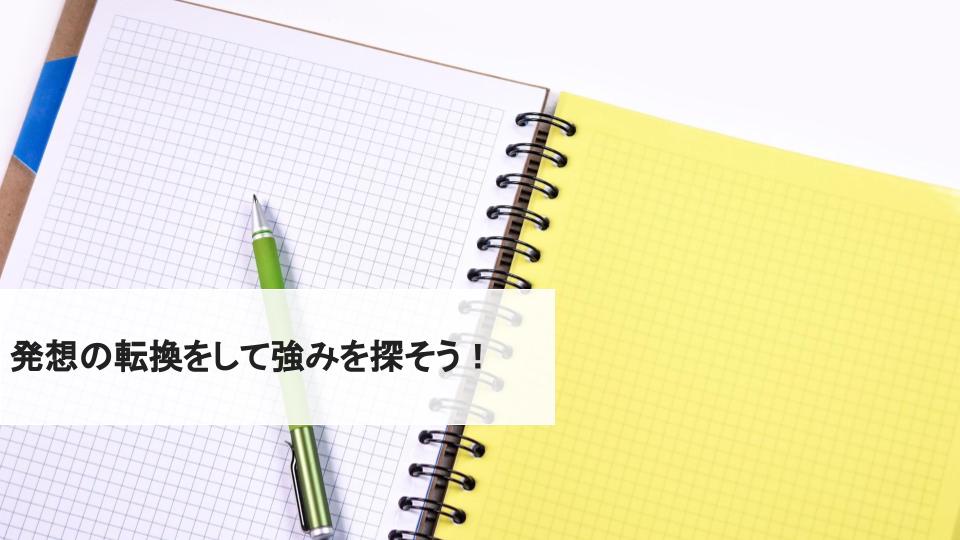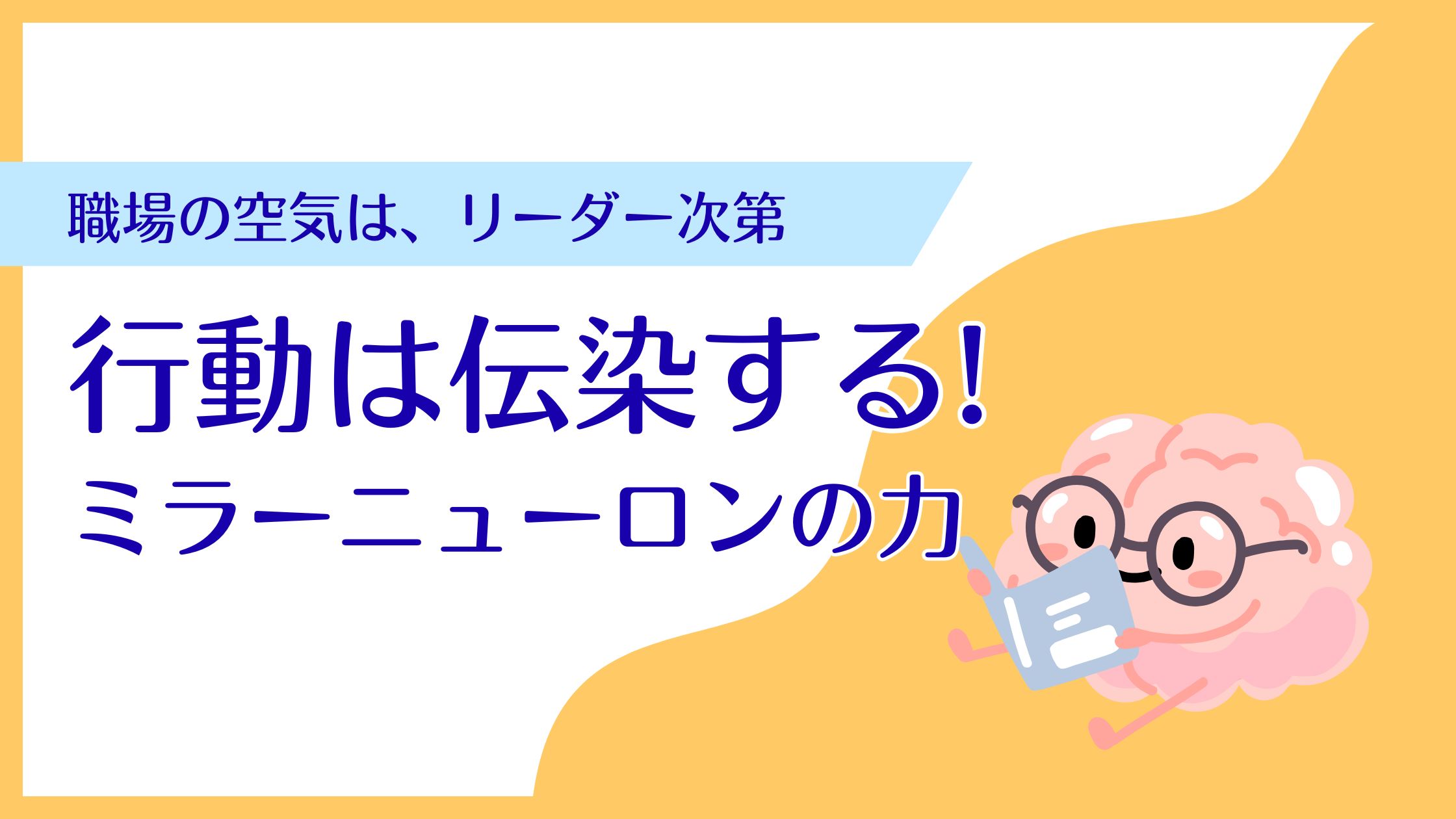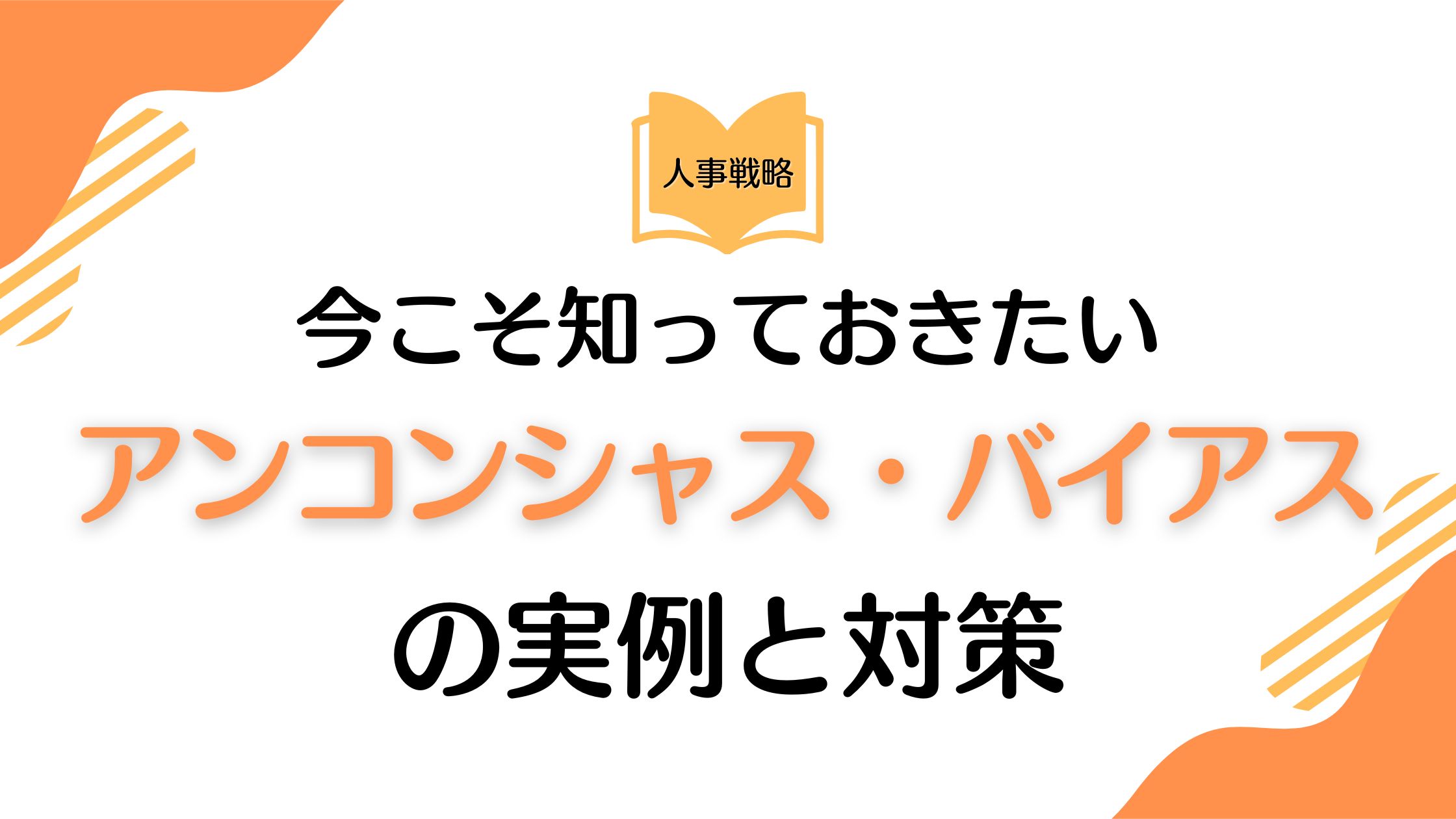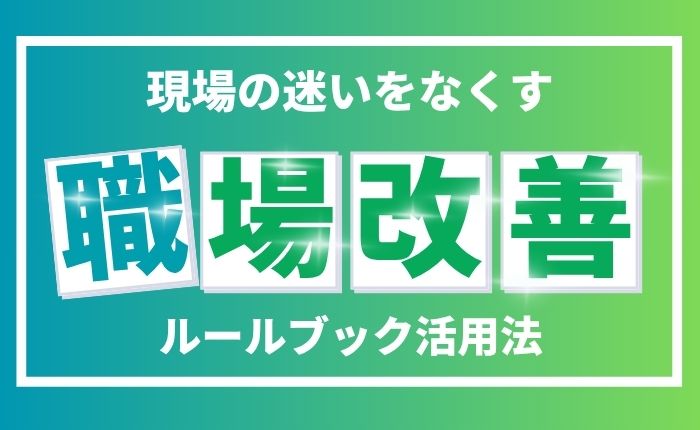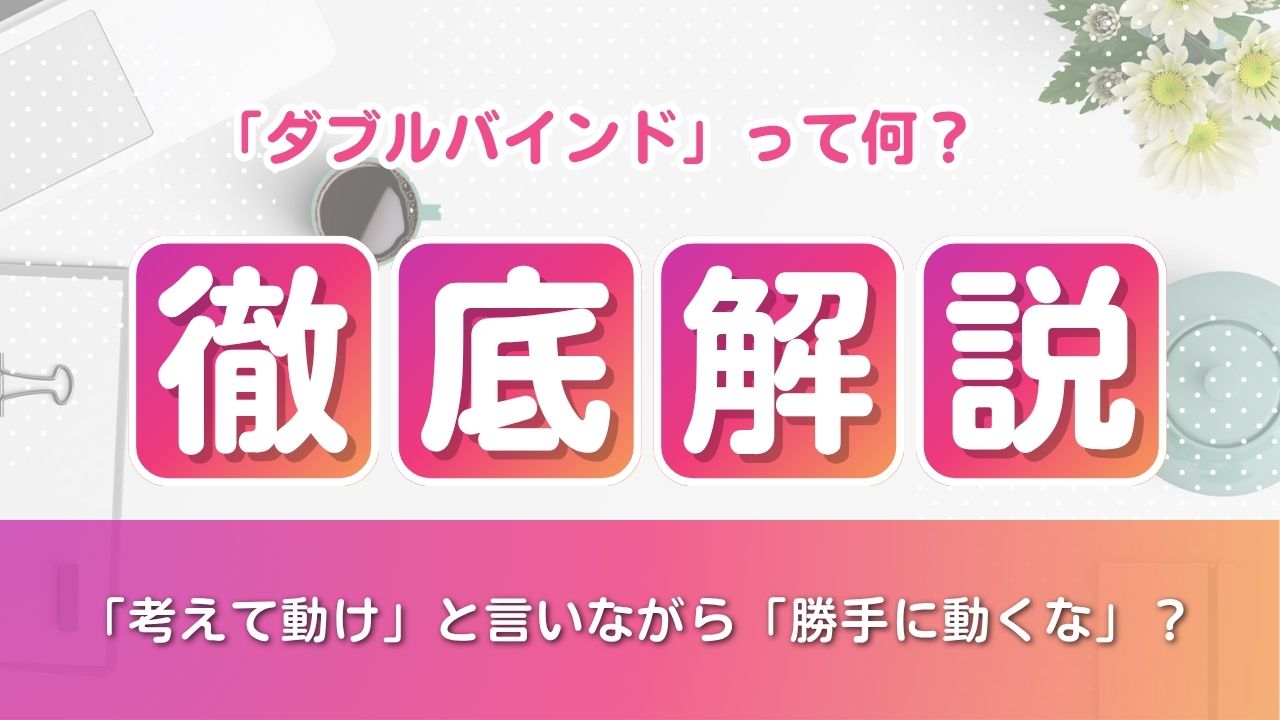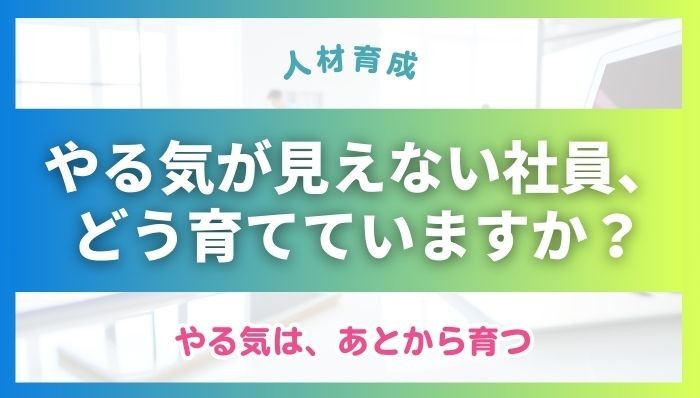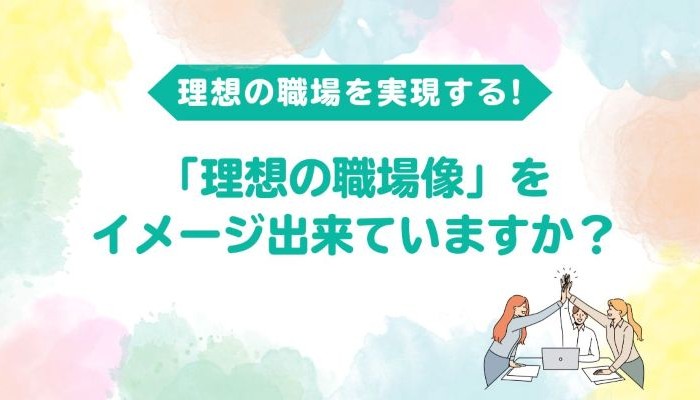制度はあるのに誰も使わない?定着率に効く“空気感”づくりのヒント
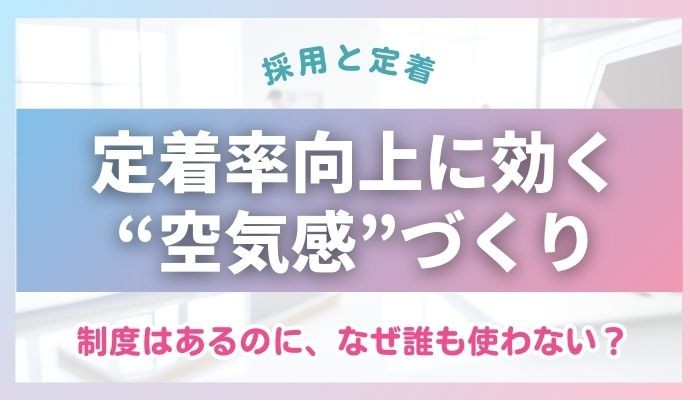
はじめに:制度はあるのに、なぜか使われない——その違和感の正体
こんにちは。
社労士として中小企業の人事労務に関わっていると、「制度はあるのに誰も使わないんです」というお声を耳にします。
育児や介護に関する制度、例えば「子の看護休暇」や「介護休暇」など、きちんと就業規則に定めていても、実際に使われる機会が少ないというケースは少なくありません。
なぜ、せっかく制度を整えているのに使われないのでしょうか?
もしかするとその背景には、「使いづらい空気」があるのかもしれません。
今回は、制度を「整える」だけで終わらせず、「活かす」ために必要な“職場の空気感”についてお話しします。
制度はある。でも、知られていない・使われていない現実
制度の“存在”と“活用”には大きなギャップがある
中小企業では、労務管理や就業規則の整備にも力を入れている会社が増えてきました。
しかし、「制度を整えただけ」では十分とは言えません。
実際には、
-
社員が制度の存在を知らない
-
制度があることは知っていても、どう使えばいいのか分からない
-
周囲に迷惑をかけるのではないかと遠慮している
という理由から、制度がほとんど活用されていないケースも多いのです。
本音では「使ってほしくない」と思っていませんか?
例えばこんなことありませんか?
「制度はあるんですけどね、誰も使わないし…正直、今休まれると困るなと思っちゃうこともあります。」
ドキッとするような本音かもしれませんが、これは決して珍しい話ではありません。
むしろ、現場では多くの方が似たような葛藤を抱えているのではないでしょうか。
中小企業にとってのリアルな事情:業務の“重み”が違う
一人あたりの業務負担が大きいからこそ起きる現象
特に中小企業では、一人の社員が担う業務の範囲が広く、代替要員の確保が難しいのが実情です。誰かが急に休んでしまうと、「あの業務、誰がやる?」「顧客対応は?」と現場が混乱してしまうリスクがあります。
だからこそ、
「使わないで」とは思っていなくても、
「今はできれば休まないでいてほしいな…」と感じてしまう瞬間があるのも当然です。
ですが、それでは今後の採用や定着において、大きな壁にぶつかることになるかもしれません。
「制度はあって当然」時代へ。これから求められるのは“使える職場”
制度が“あるだけ”では選ばれない・残らない
いま、求職者や社員が会社を見る視点は変わってきています。
以前は「制度が整っている」こと自体が魅力でしたが、
今は「それがちゃんと使えるかどうか」まで見られる時代になってきました。
-
制度はあるけれど、誰も使わない会社
-
制度があり、使った人がちゃんと評価される会社
この2社では、同じ内容の制度でも印象はまったく違います。
後者のような職場には人が集まり、そして自然と長く働いてくれるのです。
制度を活かす職場には、「安心して使える空気」がある
“空気づくり”が制度を動かす
制度を整えることはスタート地点です。
でも、それを活かすためには「使っていいんだ」と社員が安心できる空気感が欠かせません。
たとえば、
-
「お互いさま」という言葉が自然に出てくる文化
-
制度を使った社員が責められず、むしろ感謝される職場
-
制度の内容や手続きが、社内で定期的に“見える形”で共有されている
こうした空気づくりがあってこそ、制度は“絵に描いた餅”ではなく、組織の力を支える実践的な仕組みとなります。
まずはここから:制度を「使えるもの」にするワンアクション
小さなきっかけで、職場は変わりはじめる
制度そのものを変える前に、こんなシンプルなアクションから始めてみませんか?
「うちにはこういう制度があるから、必要なときは遠慮なく相談してね。」
経営者や上司からこのひと言があるだけで、社員の心の中に「使っていいんだ」という安心感が生まれます。
たとえ制度の利用がすぐにはなかったとしても、その積み重ねが職場の雰囲気を変えていくきっかけになります。
まとめ:人が定着する会社は、「制度」も「空気」も整っている
制度を整えることは、経営者の責任としてとても大切なことです。
でも、もっと大切なのは、それを「使える」状態にすること。
中小企業の現場では、「今は難しい」と感じる事情があるのも事実です。
それでも、少しずつ空気を整えていくことで、制度は社員にとっての安心材料となり、
「ここで働きたい」「ここなら続けられそう」という気持ちを育んでくれます。
制度と空気の両輪で、人が集まり、人が育ち、人が残る。
そんな職場づくりを、これから考えていきませんか?


.png)